歯科衛生士の国家試験に合格するためには?
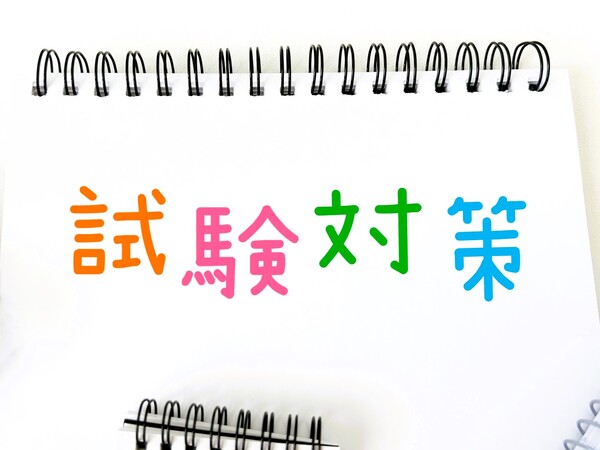
歯科衛生士は国家資格の一つですので、歯科衛生士として働くためにはまず国家試験に合格しなければなりません。
とはいえ「歯科衛生士の国家試験」と言われても、どんなものなのかなかなかイメージしづらいかもしれませんね。
歯科衛生士の国家試験はいつ、どんな形で行われるのか、どうすれば受験できるのか、今回は歯科衛生士になるために欠かせない「国家試験」について詳しくご紹介しましょう。
歯科衛生士国家試験は年に1回だけ
歯科衛生士の国家試験は年1回の実施で、基本的には3月の初めに試験日が設けられます。
令和7年(2025年)は3月2日(日)が試験日、合格発表は3月26日(水)に行われます。
試験会場は10都道府県(北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県)に設けられ、受験者は午前と午後合わせて300分(5時間)の試験に臨みます。
歯科衛生士の国家試験はマークシート形式で、午前と午後それぞれ110問の問題を150分で解答する形です。
実技試験や小論文、面接などはありません。
全220問(1問1点)の6割以上、点数で言うと132点以上得点できれば合格となり、昨年(令和6年)は合格率92.4%(7950人の受験者のうち7346人が合格)でした。
それ以前の年も合格率は90%を超えていますし、96%が合格する年もありますので、しっかりと準備して臨めば合格する可能性は高いと言えますね。
どんな勉強をすればいいの?
では歯科衛生士になるためには具体的にどのような勉強をすればよいのでしょうか。
まず重要なのは「独学では歯科衛生士になれない」という点です。
歯科衛生士は専用の器具や薬品を使っての虫歯予防処置や、歯科医師の診療のサポートが仕事です。
患者さんに対して医療行為を行う際に必要となる専門的なスキルは独学で身に付けることはできませんので、歯科衛生士になるには国が定めた養成校での3年以上の学習が義務付けられています。
つまり歯科衛生士に必要とされる知識や技術を養成校で修得し、卒業後に国家試験を受けるという流れですね。
国家試験では歯や口腔に関することはもちろん、それ以外の人体の構造や機能、疾病の成り立ちや回復過程の促進など、歯科医療に関する幅広い知識が問われます。
養成校では座学だけでなく、歯科医療の現場で実際に処置を行えるようにするための実習も行われます。
国家試験に実技はありませんが、座学で学んだ知識を深めるのに実習は大いに役立つでしょう。
国家試験対策としては過去問を解いておきたいですね。
マークシート形式であっても答えを丸暗記するのでなく、なぜその答えになるのかをきちんと考えられるようにし、苦手な分野があれば重点的に復習して克服できるようにしましょう!
なにわ歯科の国家試験対策は?
歯科衛生士の養成校には専門学校や大学、短大などがあり、全国各地で多くの学生が歯科衛生士を目指して学んでいます。
大阪の梅田にあるなにわ歯科衛生専門学校も、歯科衛生士の養成校のうちの一つです。
昼間部と夜間部を設ける本校では国家試験に向けて様々な対策を行っており、昼間部では2年次9月から、夜間部では2年次3月から、定期的に模擬試験を実施します。
模擬試験は「十分に知識が身に付いているか」「どこが苦手か」といった個々の課題の確認に役立ちます♪
また国家試験直前の2月までに十数回行われる模擬試験は予行演習にもなり、本番での緊張も減らせるでしょう。
さらに3年次11月中旬からは総合演習も行われます。
国家試験に向けての補講のようなもので、学生からの要望が多い講義を改めて行います。
これらに加え、学習面をはじめとする各学生の学校生活をしっかりとサポートできるよう、本校では担任制をとっています。
普段の学習や国家試験に向けての悩みなどがあれば気軽に相談できるようになっていますのでご安心ください!
なにわ歯科衛生専門学校では国家試験合格を目指すのはもちろん、現場で即戦力として活躍できるよう、実践的な実習も重視したカリキュラムを用意しています。
学生同士で歯科衛生士役と患者役を交代しながら実習を行う他、使用する機器も最新のものを揃えていますし、経験豊富な講師が分かりやすく丁寧に指導します。
昼間部ではダブルライセンス制度や海外研修も取り入れ、歯科衛生士としての視野も広がります。
夜間部なら仕事と資格取得の両立も可能ですよ。
最寄り駅である阪急中津駅からは徒歩2分、JR大阪駅や各線梅田駅からでも徒歩8分と、アクセス面も申し分ありません。
定期的にオープンキャンパスを開催していますので、まずは一度参加されてみてはいかがでしょうか。
皆様とお会いできるのを楽しみにしています。





